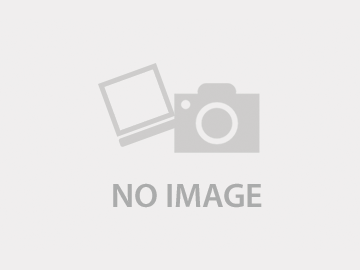終身雇用の時代は終わり、やっと多様な働き方が認められるようになってきた日本社会。
フリーランスというスタイルで仕事をしている人も増加傾向にあります。
カフェやワーキングスペースでPC一つで仕事をしている人を見かけることもよくありますよね。
とはいえ、現在会社員としてエンジニアの仕事をしている状況からフリーランスに転身することは、不安も多くリスクも大きく感じることでしょう。
この記事では、フリーランスエンジニアとしての
- 働き方
- 収入事情、税金
- キャリアや将来性
についてまとめていきたいと思います。
フリーランスエンジニアはどんな働き方をしているの?

フリーランスエンジニアは基本的に契約単位で仕事をしています。
派遣エンジニアと似ていますが、フリーランスは単独で個人的に企業と契約するため、企業には属していません。
派遣の場合は派遣元から給与を受け取りますが、フリーランスは直接契約した企業から報酬を受け取ることになります
フリーランスの収入については後ほど詳しくまとめます。
フリーランスの働き方には大きく分けて2種類あります。
一つはクラウドソーシングで仕事を受注する在宅型の働き方です。多くの方がフリーランスと聞いてイメージするのはこの働き方ではないでしょうか。
遠隔で業務にあたるため、基本的に単独で作業を進めることができる仕事に限られます。
webデザイナー、コーダー、アプリケーションプログラマの方は在宅型の仕事を比較的見つけやすいです。
もう一つは企業に常駐する形の働き方です。実はこちらがフリーランスエンジニアの働き方で一番多い形態です。
エンジニアの仕事自体はプロジェクト単位でチームとして進めることが多いため、他のプロジェクトメンバーと同様の働き方をすることが多いのです。
また、データの持ち出しなどセキュリティー面で制限も多くなるため、常駐型が主流です。
そのため、システムエンジニアやプログラマのフリーランス案件は基本的に常駐型がメインです。
フリーランスで働くメリット
収入が増える可能性が高い
会社勤めの場合、クライアントから得た報酬は会社が受け取り、上司の評価によって自分の給与が査定され、給与が決められます。
自分の業績だけではなく、組織、会社の業績など様々な影響があるため、収入を急に増やすということは困難です。
一方フリーランスの場合、クライアントとの直接契約となるため(ただし、商流による中間マージンの控除はあります)、報酬はそのまますべて個人のものとなります。
ただし、給与を会社から受け取っていた時とは違い、厚生年金や健康保険料など天引きされていたものは引かれておらず、福利厚生もありません。
確定申告などの事務作業も自分で対応する必要があるため、多少負担が増えるとも捉えられますが、収入は増える可能性が高いと考えて良いでしょう。
自分の裁量で仕事を決められる
企業に所属し、会社員として仕事をしている間は、自分の意志だけで仕事を選ぶことはほぼ不可能です。突然の転勤や部署移動もありうるでしょう。
仕事をする時間も自分でコントロールできるようになった結果、労働時間が減ったというフリーランスエンジニアは多くいます。
自分の裁量で仕事を決め、自分の強みを生かした仕事に集中できる環境を自ら作った結果、生産性が向上したとも言えるでしょう。
組織で働く場合、自分の仕事以外の管理業務を任されることもあります。
フリーランスの場合、基本的に個人プレーのため、そういった業務をカットすることが可能です。
好きな場所、好きな時間に働ける
特に在宅型のフリーランスとして働く場合、働き方の自由度がかなり上がります。
自宅でリラックスしながら、カフェでコーヒーを飲みながら、自分の集中できる時間帯に仕事に取り組むことが可能です。
また、常駐型のフリーランスの場合も、通勤先やフレックスタイム制の有無などを確認したうえで仕事を選ぶことができるため、会社勤めよりも自由に働き方を選べるでしょう。
フリーランスで働くデメリット
収入が不安定である
月々決まった額を給与として受け取る会社員と違い、プロジェクト単位で報酬を得るため、収入が安定しづらいのはフリーランスのデメリットと言えるでしょう。
仕事の受注がうまくいかなくとも、会社勤めであれば月の給与は保障されます。病気や怪我で働けなくなったとしても、生活は保障される制度が福利厚生で整えられています。
フリーランスとの報酬が会社員のころよりも増えたと言っても、そこから諸経費は出ていきます。そのため、仕事の受注状況によっては収入の増減があると考えておいた方が良いでしょう。
社会的信用が得にくい
フリーランスの大きなデメリットの一つとして挙げられることが多いのがこの点です。
住宅ローンを組む際は特に大きな弊害となりうるでしょう。
住宅ローンの審査基準は細かく分類されていますが、その中でも勤務先や勤続年数は重要な審査基準とされています。
そのため、フリーランスはローン審査が不利と言えます。
ただしこの審査基準は日本の終身雇用時代から大きく変わっておらず、時代と逆行する基準だという見方も強くなってきているため、そう遠くない未来に改善される可能性が高いでしょう。

税金・保険などを自分で管理しなければならない
企業に属している間は、年末調整で保険会社から来た書類を提出したり、社内のイントラネットに入力しておしまいの簡単な作業ですが、フリーランスとなるとそうはいきません。
厚生年金ではなくなり国民年金に自分で加入手続きをし税金を支払い、健康保険も自分で加入し備える必要が発生します。
また、確定申告のために領収書などを保管し、帳簿を作るといった事務作業も自分で対応することになります。
慣れてくると勝手もわかってきますが、慣れるまではわからないことも多く負担と感じることもあるでしょう。
雇用保険がない
フリーランスは個人事業主ですから、雇用保険を支払わない代わりに雇用保険を受給することはできません。
ですから、会社を退職した元サラリーマンがハロワークに駆け込めば、雇用保険で生活を維持できることに比べ、フリーランスは仕事を休めば完全に無収入です。家族を養わないといけない、ローンを払わないといけないという人にとっては、雇用保険の有無は滅茶滅茶大きなデメリットとなります。
→【midworks】![]() ・・・フリーランスであっても正社員並みの福利厚生や保障が受けられるフリーランスエージェントです。
・・・フリーランスであっても正社員並みの福利厚生や保障が受けられるフリーランスエージェントです。
フリーランス・エンジニアから正社員に戻れるか?
私も、フリーランス・エンジニアから正社員に戻ったケースを見たことがありますが、はっきり言って年齢が上がってくると再就職難しくなり、再就職できたとしても条件は良くないということになりかねません。
これについては、一般的な転職と同様です。IT業界は人手不足が続いていますが、一方でエンジニアは年齢が上がるとその市場価値は逓減していきます。
その昔は35歳定年説がありましたが、現在では35歳とは言わないまでも40歳を過ぎると、かなり市場価値は下がるのです。
ここら辺については、フリーランス時代にどのような働き方をしてきたかにもよるのですが、在宅で働いていた人が、絶賛炎上中のSIer開発案件に入るというのは、雇う方としても当のエンジニアにもリスクがあります。

SES会社でも、高齢のエンジニアは敬遠されます。そもそも、元からいた社員も高齢になれば、クビ候補になる位ですから。
フリーランス・エンジニアから正社員に戻るために必要なことは、やはり会社が求めているスキルと高度にマッチするか否かとなります。コボルばかりやっていた人がオープン系の開発が中心の会社に入るのが難しいということは誰でも分かると思います。一方で、ある特定の業種や業界、原価計算や経理、生産管理などの業務領域などに詳しく、Java等の主要言語をマスター人であれば、ある程度年齢がいっていても手を挙げる会社は少なくないでしょう。
ここまでのまとめ
収入や生活の「安定」を強く求める方にとっては、フリーランスという選択肢はとてもリスクの大きなものに感じられるかもしれません。
一方で自分のスキル向上を目指したい、自分のペースで働きたいと考えている方にとっては、フリーランスという選択肢は意味のあるものでしょう。
働くにあたり、自分がどちらを重視するかということをしっかりと考え抜きましょう。
次に、 フリーランスの収入事情、税金についてみていきます。
フリーランスエンジニアの収入事情、税金

フリーランスエンジニアの平均年収は?
IT系フリーランスエンジニアの平均年収は下記の通りとなっています。
- SE 840~960万円(月平均単価 70~80万円)
- プログラマ 720~840万円(月平均単価 60~70万円)
- Webデザイナー 600~720万円(月平均単価 50~60万円)
- コーダー 480~600万円(月平均単価 40~50万円)
ご覧の通り、SEは仕事の難易度や市場に存在する人材の人数が少ないことなどから、相場は高い傾向にあります。
ただし、このデータはIT系転職エージェントが公開しているものの集約ですから、エージェント利用者の年収が元になっています。つまり、クラウドソーシングを使っている人や縁故を頼りにしているフリーランスエンジニアは含まないということです。ですから、フリーランスエンジニア全体で見ると、実はもう少し年収は低い可能性があります。
次に、年代別で平均年収を比較してみましょう。
- 20代 696万円 (正社員平均年収の1.84倍)
- 30代前半 780万円 (正社員平均年収の1.64倍)
- 30代後半 816万円 (正社員平均年収の1.42倍)
- 40代前半 840万円 (正社員平均年収の1.32倍)
- 40代後半 876万円 (正社員平均年収の1.31倍)
- 50代前半 660万円 (正社員平均年収の0.96倍)
- 50代後半 600万円 (正社員平均年収の0.88倍)
特徴的なのは、若ければ若いほど会社員として働くエンジニアよりも収入が多い点です。
福利厚生や保険がないというデメリットやリスクはありますが、若いうちにフリーランスに転向し経験を積むメリットは大きいと言えるでしょう。
会社員とフリーランスの年収の差はどこから出てくるのか?
元請けから当のエンジニアに直接お金が支払われるのではなく、間に会社が数社入っている可能性があります。所謂「多重下請け」というという状況ですが、これを商流といいます。
商流が深い場合、中間マージンをそれだけ抜かれることになりますので、年収がどんどん下がることになります。逆に、浅ければ浅いほど、年収が上がりやすいとも言えます。商流はフリーランスエンジニアの年収を大きく左右するのです。
会社員の場合、商流に加えて会社の経費を負担しなければなりませんから、フリーランスエンジニアと比べると年収は低くなってきます。20代~40代における年収の差はここに大きな原因があります。
一方で、50代になると会社員の年収が逆転します。これは、会社員では昇進によって1プレイヤーではなく管理職になるというキャリアパスがあるからです(年功序列ともいいますw)。
フリーランスの場合、生涯1プレイヤーでしかありませんから、エンジニアとして市場価値が落ちる50代以降は年収が下がってしまう訳です。
フリーランスエンジニアが払う税金について
会社員時代はすべて総務で対処され、給与からの天引き、年末調整で差額が返金される仕組みになっている税金。
フリーランスになるとこれらはすべて自分で対処しなければなりません。
複雑で面倒だと思う点もあるかもしれませんが、やらなければ罰則もあるためしっかりと押さえておきたいポイントです。
フリーランスエンジニアが払う税金は大きく分けて下記の通りです。
所得税
年間の収入から、経費、基礎控除、その他控除を除いた所得に課税されます。よって、所得が多ければ多いほど支払う税も多くなります。
青色申告をすることで最高65万円の控除を受けられます。
なお、働き方の多様性に対応するために2020年1月から所得税について一部変更があり、フリーランスにとっては減税というメリットが生じています。
所得が2400万円以下の人に対し基礎控除が会社員と同様の48万円に引き下げられており、その分課税所得が減り減税となります。
住民税
都道府県民税と市町村民税を合わせた総称です。所得税と違い、前年の収入に対して課税されます。
自治体によって課税基準が多少異なる場合や、均等課税される項目が存在するケースもあるため、金額はばらつきがあります。
フリーランスの場合、より住民税が安い土地に引っ越すという手段を取る人も中にはいるようです。
国民健康保険税
国民健康保険加入者が支払う費用です。世帯ごとに、前年所得や被保険者数、加入期間、資産等に基づいて計算されます。
個人事業税
個人事業主の所得が230万円を超えた場合に都道府県に納める税金です。
業種ごとに納税額が異なるため、確認をしましょう。
消費税、そしてインボイス制度の影響とは
これまでは2年前の年間売上が1000万円を超えた場合に納めることになっていました。
しかし2023年10月から「インボイス制度」が導入されることになり、これまで売上1000万円以下の免税業者として仕事を受注してきたフリーランスに影響が出ることが予想されています。
消費税は売り上げの消費税から、仕入れや経費の消費税を引いた額を納税することになっています。つまり、差し引ける仕入れや経費の消費税額が少なくなると、その分納税額が増えます。
インボイス制度が導入されると、発注側は受注先のフリーランスから事業登録番号が記載されたインボイスを受け取らなければその消費税を差し引くことが出来なくなってしまうのです。
この制度導入によって、免税業者としてやっているフリーランスでは節税が出来ないため、案件受注の難易度が上がってしまうリスクが考えられます。
また、消費税分を差し引いた金額を提示される可能性もあり、報酬額が下がることも懸念されます。
これらの事を回避するためには、課税業者に切り替えておく、事業を縮小するなどの対策を考えてく必要がありそうです。
ここまでのまとめ
いかがでしたでしょうか。
フリーランスエンジニアになると、仕事に対する報酬としての収入は増えますが、会社員として働いていた時よりも税金に対して意識を向けることが必要になります。
経費の計上の仕方、消費税のインボイス制度導入対策等、税理士などプロの力を借りながら自分で様々な知識をインプットしていきましょう。
フリーランスエンジニアの将来性

フリーランスの人口は増加し続けている
クラウドソーシングのトップ企業であるランサーズの調査によると、エンジニアだけに関わらず様々な業界でフリーランスとして働く人の人口は年々増加傾向にあるそうです。
2018年の調査では副業・兼業を含むフリーランス人口は1,119万人となり、日本の労働人口の17%を占めています。
フリーランスの経済規模は今や20兆円を超えています。
ちなみに外に目を向けてみると、アメリカでは労働人口の約35%がフリーランスという働き方を選択しているそうです。経済規模は日本円にして154兆円。
将来的にはフリーランスがフリーランスではない人の人数を超えるタイミングも訪れるという見方もあるほど、フリーランスという働き方を選択する人は増えています。
もちろん日本もその後を追うだろうと考えられています。
これから言えることは2つです。競合のフリーランスエンジニアが増える、フリーランスエンジニアという存在を認知する会社が増え市場規模が増加する、です。
競合が増えれば、それだけ仕事を取るのは大変になりますが、現在IT市場自体が活況ですので、あまり気にする必要はなさそうです。
そして今、IT系の人材不足に悩む企業が非常に増加しています。そのような会社の中には社員として毎月固定で高いお金を支払うことに負担感がある会社も多くあります。
そういった会社は自ずと、フリーランスエンジニアに発注することが選択肢になってきます。
今後確実にフリーランスエンジニアの需要は増えてくると予想されます。
パラレルワーカーが増加している
フリーランスは大きく4種類に分類されます。
- 自営業で自ら事業運営をしているオーナー
- 独立して特定の勤務先がない状態で仕事をするフリーワーカー
- 一般企業に勤務しながら、副業としてフリーランスの仕事をするすきまワーカー
- 2社以上の企業と契約をしているパラレルワーカー
この中でも最近特に伸びを見せているのが、業務委託という形で2社以上の企業と契約して仕事を数パラレルワーカーです。
フリーランスエンジニアの場合、パラレルワーカーに該当する働き方を選ぶ人が多く、フリーランスの道を選ぶエンジニアが増加傾向にあると考えることができます。
そういった影響もあり、フリーランスを活用するIT企業も増えてきています。
アメリカではプロジェクト単位で人を集めるという方法も定着してきており、フリーランスエンジニアにとっては仕事を得やすい環境が作られてきています。
日本においてもこの動きが広がっていく可能性は十分あるでしょう。
こういった流れから考えても、仕事を受注できる人脈を作れている人にとっては特にフリーランスへの転向はしやすい時期と言えるでしょう。

予算が大手より少ない中小企業は、在宅でも構わないからやや単価は安めで発注したいところが多いみたいです。今は、リモートでも稼働状況が分かりますしね。
フリーランス向きの人と会社員向きの人の違い
いくらフリーランスに転向しやすい状況と言えども、人には向き不向きがあります。
フリーランスという働き方が向いている人と向いていない人には大きな違いがあります。
なんとなく自由がないし、給与も上がらないし窮屈だと考えてフリーランスへの転向を考えている方は、今一度立ち止まり、自分がフリーランスとして頑張れるかどうかを冷静に考えてみてください。
まずは下に並べる項目にどれだけ自分に当てはまるかを確認してみましょう。
| □ | とにかく自分のペースで仕事をしたい |
| □ | スケジュール管理、自己管理はできる方だ |
| □ | 営業力、コミュニケーション能力は問題ない or 得意である |
| □ | 人見知りではない、初めての場所が苦手ではない |
| □ | 人からの指示がなくても仕事は進められる |
| □ | 一人で仕事をすることは苦ではない |
| □ | 収入が不安定になっても持ちこたえられそう |
| □ | 細かい数字の管理は得意 |
チェックが多ければ多いほどフリーランスとしての働き方は向いていると言えます。
逆にチェックが少なければ、フリーランス一本で仕事をしていくことはまだ時期尚早です。
最初の方でも触れた通り、フリーランスのデメリットとして、
- 収入が不安定である
- 社会的信用が得にくい
- 税金・保険などを自分で管理しなければならない
といったことが挙げられます。つまり、これらに不安や苦手意識を感じる方はフリーランスとして仕事をするのは向かない可能性が高いと言えます。
特に収入に関しては生活を大きく左右することでもあるため、大きな不安が伴うのであれば無理をしないでタイミングを計る方が良いかもしれません。
また、フリーランスとして成功するためには、自分で営業をして案件を獲得する力が必要です。
営業を代行してくれるフリーランス専門のエージェントが存在するので、そういったサービスを利用するのも一つの手ですが、身に付けておいた方が後々役立つ力であることには違いありません。
そしてフリーランスとして働く上で最も大きな壁として立ちはだかるのが、孤独と「敵は自分である」ということです。
チームで達成の喜びを分かち合うような瞬間もなければ、上司もおらず他人の目もないためサボろうと思えばいくらでもサボれてしまう環境です。
そういった孤独感や、自己管理能力を問われるような場で心が折れてしまう恐れがあるのであれば、しばらくは会社員としてエンジニアを続けた方が良いかもしれません。
一人で好きな場所、好きな時間に働くことができるからこそ、自分を管理しコツコツと継続していくことが成功する上で求められるのです。
もしこれらに苦手意識がなく、むしろ自分に合っていると思う部分があるのであれば、ぜひフリーランスとしての一歩を踏み出してみましょう。
キャリアや将来性のまとめ
フリーランスエンジニアはこれからますます増えていくことが予測されます。
今後フリーランスへの転向を検討される方は、まずはフリーランスとして求められる素養を身に付け、自己管理を徹底していきましょう。
フリーランスの仕事自体はこれからますます普及していくことでしょう。
その中でご自身の価値を最大限に発揮し、自分らしく自分のペースで仕事が出来れば最高ですよね。
これからの社会で生き残っていくためにも、自分の可能性を最大限に広げて仕事を選べるよう、日々努力していきましょう。